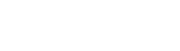21年度ZEH実績
利根川源流からエネルギー革命を!
沖縄のピザ屋さんから2度目の「無有の薪」ナラの注文がありました。「各地の薪を使ってみたけれど、一番火持ちが良いので再度購入します」とのことです。神奈川の古民家(茅葺き)からは、囲炉裏用として利用し「はぜることもなく、火持ちも良かった」とのことで通年購入を検討しているとHP註1から連絡をくれました。
近隣の購入者は薪置き場の看板を見て「軽トラック」で来社される方が多い。「たくみの里」への観光で偶然看板を見つけ、看板を立てた翌日に大口購入者が現れたこともありました。ユネスコエコパーク註2のロゴマークは行政の担当者も「大きくて目立つ」と喜んでくれました。
みなかみ町では町内の森林資源の有効活用の促進等を目的として、4年前から薪ストーブ購入補助金制度がスタートしました。この制度ができてから薪ストーブや薪の販売が急速に増えています。行政との協働が顕著な成果として現れています。
足元の里山で埋もれていた樹木を薪に変えることで、町内だけでなく全国の薪利用者と繋がりができました。一本の樹木から世界が広がります。
註1 http://www.koubou-muu.com 作成の一部はみなかみ町の補助金を利用している。
註2正式名を生物圏保存地域(BR:Biosphere Reserves)といい、1976年(昭和51年)に開始されたユネスコ人間と生物圏(MAB:Man and the Biosphere)計画のプロジェクトの一つで、日本では親しみやすいように「ユネスコエコパーク」と呼ばれています。
河合純男 元みなかみ地域エネルギー推進協議会事務局長
写真キャプション ユネスコエコパークのロゴを入れた